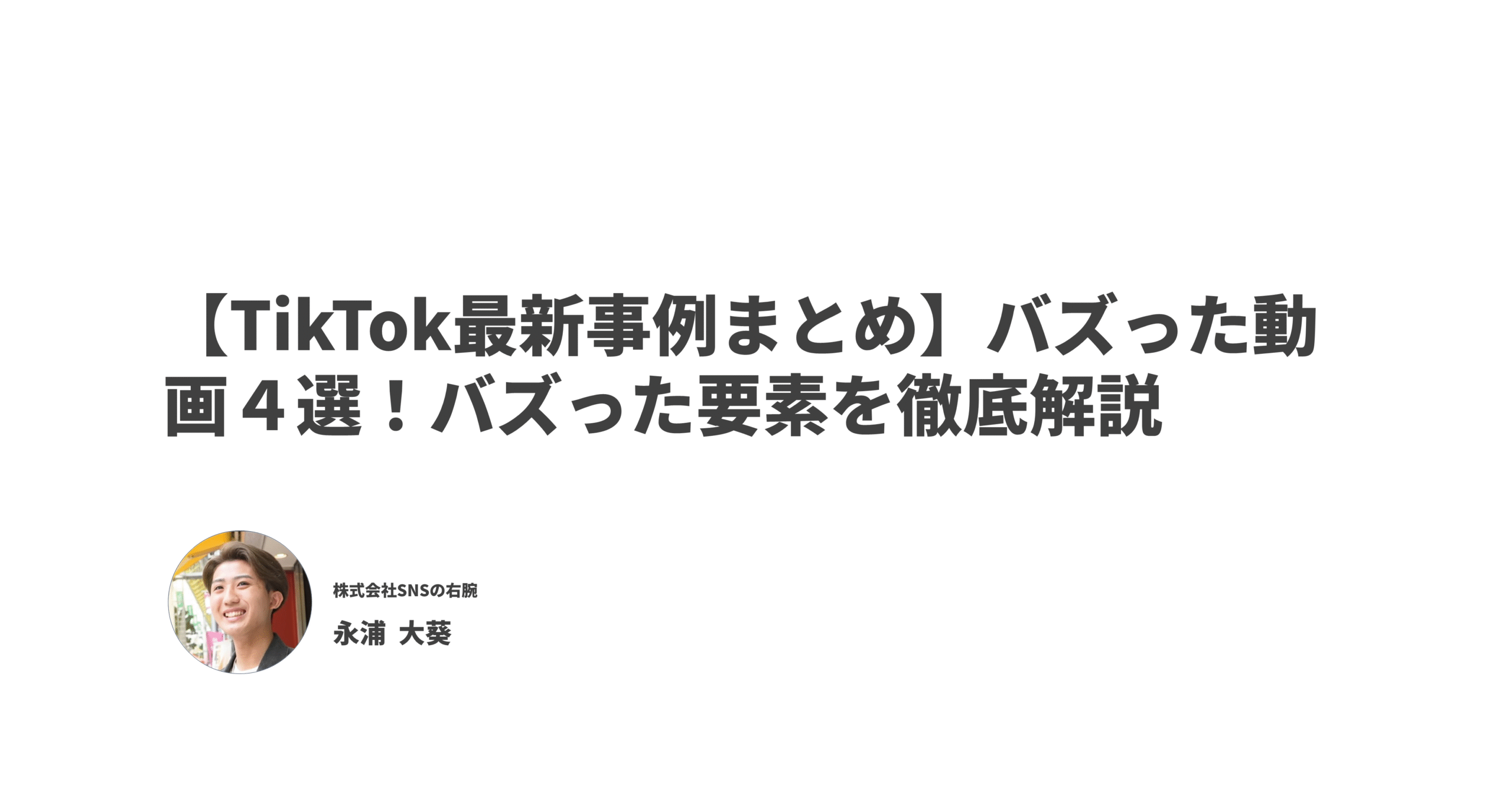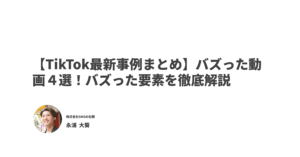本記事では、2025年に大きな反響を獲得した企業のTikTokアカウントを5本厳選し、「なぜ伸びたのか」を再現可能な要素に分解して解説します。
今回取り上げる動画
- 【事例①】美容クリニックの新入社員
- 【事例②】かなぺ / 美脚ウォーキング
- 【事例③】六本木/銀座 体の体調を整えるヘッドスパ
- 【事例④】パリピ廃業ホテル
それでは、各事例の「バズった要素」を具体的に見ていきましょう。
①美容クリニックの新入社員
「美容クリニックの新入社員」というTikTokアカウントは、わずか11投稿で3,803フォロワー・2.6万いいねを獲得。採用広報の事例として。特にSNSを通じて採用を強化したい企業は、このアカウントから学ぶべき点が多いでしょう。今回はその中でも、とりわけ優れていると感じた2つのポイントに絞って解説します。
1.ネーミング戦略:個人化が生む親近感
SNSにおいてアカウント名は第一の接点であり、興味を持たれるかどうかを決める入口です。
「美容クリニック」という法人名だけでは、広告色が強まりユーザーに売り込みと受け止められる可能性が高いでしょう。そこであえて「美容クリニックの新入社員」と名付けることで、個人を想起させ、キャラクター化された存在を前面に押し出しています。
- 公式アカウント=無機質な広報
- 新入社員アカウント=人間味あるストーリー
というコントラストが、視聴者にとって絡みやすさや共感しやすさを生み出しています。さらに「新入社員」という肩書きは、誰もが経験したことのある「新人の不安」「初々しさ」を連想させ、心理的距離を縮めます。
これは、Z世代をターゲットにした採用広報で特に有効。匿名の企業よりも、等身大の誰かをフォローしたくなる心理が働くためです。
2.撮影アングル戦略:視点設計が生む没入感
もう一つの優れた点は、視聴者視点に近いアングル設計です。動画は基本的に本人の視線に近いカメラアングルで撮影されており、自分がその場にいるような没入体験を与えます。近年、TikTokではvlog形式が急増し、従来の「顔出し+定点カメラ」型コンテンツは埋もれがちですが、一人称視点を取り入れるだけで自分ごと化される体験型コンテンツに変化させられるのは非常に巧みです。
人の脳は俯瞰映像よりも一人称映像に強く反応し、まるで自分がその体験をしているかのように錯覚します。これにより感情移入や記憶定着率が高まり、採用文脈で言えば自分がこの職場で働く未来を疑似的に体験させられるのです。またTikTokのアルゴリズムは平均視聴時間や離脱率を重視するため、没入しやすい映像は最後まで見られやすく、拡散力が高まりやすいという点でも合理的です。
このような「視点設計」は他業界でも成果を上げています。飲食業では新人バリスタの目線でコーヒーを淹れる映像、観光業では新人ホテルスタッフの1日を一人称で描いた動画、教育業界では新任教師の授業準備を目線カメラで伝える事例などがあり、いずれも自分ごと化によって応募者の心理的障壁を下げています。
視点を工夫することは単なる映像の小技ではなく、認知科学的に感情移入を生み、アルゴリズム上の優位性を獲得し、さらに採用候補者に「未来の自分」をシミュレーションさせる力を持っています。だからこそ「美容クリニックの新入社員」は、採用事例として他業界にも応用できる普遍的なモデルだといえるのです。
そもそも採用広報は時代とともに大きく変化しています。数年前まではTikTokで「給料の高さ」や「待遇の豪華さ」を前面に押し出すスタイルが流行しました。これは当時の求職者が「経済的安定」を最優先にしていた時代背景を反映しています。しかし、いまは状況が異なります。給与水準だけでは人は動かず、求職者が本当に知りたいのは、企業が掲げる数字や立派なスローガンではなく、もっと生活に近い日常のリアリティです。
具体的には、ライフワークバランスはどうか?職場の雰囲気は自分に合うのか?社員はどんな一日を過ごしているのか?といった「働く自分」を想像するための情報です。こうした疑問に答える最も自然な方法が、新入社員の目線で日常を切り取って見せることです。視聴者は映像を通じて自分を重ね合わせ、働く姿をシミュレーションします。その結果、安心感や親近感、さらには「自分もここで働きたい」という憧れの感情が生まれるのです。
これは単なるトレンドではなく、採用活動における価値基準のシフトを示しています。かつては「条件提示」で動いていた人材市場が、いまは「共感」と「自己投影」で動く市場へと移行している。だからこそ、リアルな日常を映し出す広報が強いのです。
②かなぺ / 美脚ウォーキング
こちらのアカウントは「美脚」に特化して発信している専門アカウントです。今回取り上げる動画は 9万いいね/424万回再生 を突破しており、明確にバズを生み出した成功事例といえます。
詳しい解説は後ほど行いますが、今回のポイントは「美脚」というテーマに限らず、美容系のアカウント全般に応用可能な普遍的な仕組みが多く含まれている点です。美容・ダイエット・ヘアケア・スキンケアなど、幅広いジャンルで活用できる内容になっていますので、ぜひ参考にしてみてください。
1.定量的な差別化
まず前提として、SNSにおいて「定性的な差別化」はほとんど意味を持ちません。
たとえば飲食店の「料理の味」は本来であれば決定的な差別化要素です。しかし、SNS上では味覚を直接伝えることはできません。つまり、ユーザーに届くのは「美味しいかどうか」ではなく、その美味しさをどう可視化し、定量的に示すかなのです。
この構造は美容室でも同じです。近年流行した「街中で声をかけて即興でイメチェンする企画」や「ビフォーアフターの比較投稿」は、その典型例といえます。髪質や技術の繊細な差異を文字や言葉で伝えるのではなく、変化量を視覚的に示すことで差別化を成立させています。
飲食店においても同様で、どれだけ美味しい料理を提供していても、SNSで拡散されやすいのは「写真の撮り方が工夫されている料理」や「PRに長けたお母さんが作った家庭料理風のご飯」です。なぜなら、味そのものは伝わらないからです。SNS上で勝負するには、「見た目」「盛り付け」「構図」など味以外の要素を定量化して届ける必要があるのです。
つまり、味は画面越しには届きません。届けるためには「おいしそうに撮影する」「カラフルに盛り付ける」「かわいい容器を使う」といった、味を間接的に保証する記号を設計する必要があります。たとえば「かわいいから写真を撮りたい」という動機は、まさに味覚ではなく視覚的な定量化によって購買意欲や拡散力を生み出しているのです。
1-1実例で見る定量的差別化
▪フィットネスジム
定性的:「トレーナーが優秀」「環境が整っている」では伝わらない
定量的:「2ヶ月で−8kg」「筋肉量+10%」
SNS投稿:Before/Afterの身体比較写真、体重計の数値動画、30日間チャレンジ企画
▪美容クリニック
定性的:「技術が丁寧」「仕上がりが自然」では伝わらない
定量的:「施術後のリピート率95%」「症例数3,000件」
SNS投稿:顔の左右比較、施術前後のスライド写真、症例数のカウントアップ動画
・学習塾/英会話
定性的:「指導がわかりやすい」では伝わらない
定量的:「偏差値+15」「英検合格率90%」
SNS投稿:テストの点数推移グラフ、合格者数カウント動画、生徒の1分間英語スピーチ動画比較
・アパレル/ファッション
定性的:「デザインがかわいい」「質が良い」では伝わらない
定量的:「発売初日に完売」「再販希望コメント3,000件」
SNS投稿:購入者のレビュー数スクリーンショット、在庫カウントダウン、着回しパターン◯通りの動画
・旅行/ホテル
定性的:「景色が綺麗」「雰囲気が良い」では伝わらない
定量的:「口コミ評価4.8」「年間来訪者数50万人」
SNS投稿:サンセットのタイムラプス動画、レビュー件数を映した画面、客室からのビフォー(昼)/アフター(夜景)の比較
③六本木/銀座 体の体調を整えるヘッドスパ
本アカウントはヘッドスパ領域に特化しているものの、フォロワー数3.4万人、平均エンゲージメント(いいね数)20万超という卓越した成果を継続的に記録しています。これは単なる一時的なバズではなく、コンテンツ設計や演出手法が体系化されていることの証左です。
さらに注目すべきは、その発信内容がヘッドスパの枠を超えている点です。リラクゼーションやエステといった「癒し」産業全般においても適用可能なナレッジが内包されており、業種横断的に活用できる汎用性を備えています。
自社の施策に落とし込むことで、単なる模倣にとどまらず「なぜこのアカウントがこれほどまでに数字を出せているのか」を抽象化し、自社の文脈に合わせて再現・拡張していくことが可能です。
1.施術を「視覚化」するという発想
ヘッドスパをはじめとするリラクゼーション施術は、従来「気持ちいい」という一言で語られてきました。しかしこの表現は曖昧で、施術の価値を可視化できないがゆえに、利用者以外の第三者にとっては共感や理解が難しい領域でもあります。
ここで有効なのが「施術プロセスの視覚化」です。カメラを通じて施術の一部始終を丁寧に記録することで、視聴者は“結果としての快感”を想像するだけでなく、“快感を生み出す手技そのもの”を追体験できるようになります。単なる「気持ちよさの訴求」から、「なぜ気持ちよさが生まれるのか」という因果関係までを提示する点に大きな意義があります。
さらに、この視覚化は施術を受ける本人にとっても新たな価値を生みます。自分では見えなかった指の動きや圧のかけ方を客観的に知ることで、「この心地よさはこうして生まれていたのか」と理解が深まる。つまり、“体感”という主観に、“視覚情報”という客観を掛け合わせることで、施術の満足度そのものが拡張されるのです。
加えて、視覚化はマーケティング的にも「サービスの再現性」を伝える強力な武器となります。人は五感のうち、視覚と聴覚から約8割の情報を得るとされます。施術の様子を映像と音声で届けることは、未体験の視聴者に「自分が施術を受けているような錯覚」を生じさせ、疑似体験を通じた信頼感や来店意欲を醸成します。
1-1視覚 × 聴覚による没入感
さらに注目すべきは、映像内に自然に組み込まれる施術者の声の存在です。
「なんじゃこりゃ、ガチガチですね」
「うわ、目の疲れがすごいですね」
といった一見何気ない言葉は、単なる状況説明を超えて施術のリアリティを聴覚経由で翻訳していると言えます。
この音声的ナラティブは、視聴者の想像力を喚起し、目で見ている映像と耳で聞く声が同期することで「自分が今まさに施術を受けている」ような錯覚を生み出します。つまり、視覚情報だけでは届かない体感の質感を、聴覚が補完しているのです。
さらに重要なのは、このコミュニケーションが宣伝的に加工されたコピーではなく、施術者と顧客の自然な対話として成立している点です。過剰な広告表現に依存せずとも、施術者の驚きや共感がそのまま「サービスの価値」を代弁する。結果として、強制感のないストーリーテリングが実現され、視聴者はブランドへの信頼を無意識に高めていきます。
視覚 × 聴覚の両輪によるこの没入的体験は、単なるコンテンツ演出にとどまらず、「体感価値をいかに外部に翻訳するか」というリラクゼーション業界全体の課題に対するひとつの解答でもあるのです。
④パリピ廃業ホテル
13万フォロワーを抱える「沖縄の廃業物件を再生する」趣旨のアカウント。魅力は、老朽ホテルの再生を物語化し、ゼロ→イチ→黒字化までのプロセスを公開している点にあります。
日々の意思決定・失敗・改善を連載形式で見せることで、視聴者を観客から当事者へと転換し、応援=予約・購入・支援に自然接続。ストーリー消費をそのまま売上導線に変換する設計が秀逸です。
このモデルは、店舗・ホテル運営に限らずあらゆるローカルビジネスで再現可能。
「課題の提示 → 再生プロセスの公開 → 視聴者参加(投票・命名・内装案募集) → 事前予約/EC/スポンサー募集」までを一本のナラティブで束ねることで、ファン形成と収益化を同時進行できます。
それでは、詳しく解説していきます。
1.ストーリー開示系アカウントに不可欠なエンタメ設計
ストーリーを開示するタイプのアカウントを伸ばす上で決定的に重要なのは、いかに視聴者を巻き込み、ワクワクさせるかというエンタメ性です。単なる進捗報告ではなく、「次はどうなるのだろう?」という物語的期待感を仕掛けられるかどうかが、成長の分水嶺になります。
このアカウントの優れている点は、そのエンタメ要素が明確に設計されていることです。
例えば過去の投稿では、
「助けて、もう私のホテルにお金が残っていません」
といった破綻寸前の状況を赤裸々に公開し、危機を物語化して提示しました。
ここでいうエンタメは「面白い」だけを意味しません。むしろ、失敗・葛藤・弱さの開示もまた重要なエンタメ要素なのです。人は「成功」よりも「失敗や不安定さ」に感情移入しやすく、弱さを共有することで一気に物語の当事者意識を持ち始めます。
結果として、視聴者はただのフォロワーではなく、再生の物語を一緒に歩む仲間へと変わり、ワクワク感と応援意欲が生まれる。これこそがストーリー開示系アカウントの本質的な伸び方だといえます。
弊社と共にSNSを伸ばしませんか?
株式会社SNSの右腕では、これまで累計100社以上のSNS運用を支援してまいりました。
X(旧Twitter)・TikTok・Instagramといった主要プラットフォームに精通し、スタートアップから上場企業まで幅広い支援実績があります。
特にこのような企業様におすすめです
- SNSを戦略的に活用し、採用力を強化したい企業様
- 経営者個人の発信力を高め、信頼を醸成したい方
- ブランド認知を広げ、競合と差別化を図りたい方
SNSは単なる発信手段ではなく、「採用」「集客」「ブランド構築」を同時に推進できる経営資源です。私たちは貴社の理念や背景を深く理解し、伴走型で成果につなげていきます。
| 2025.08.29 【SNS運用は必須?】企業のSNS活用のメリットを徹底的に解説 |
| 2025.09.01 なぜ彼らはバズったのか?企業アカウントX運用の成功事例と戦略分析 |
| 2025.08.25 X運用代行おすすめ会社!費用や業務内容、強みを徹底比較! |